自ら食材を作る事の楽しさ
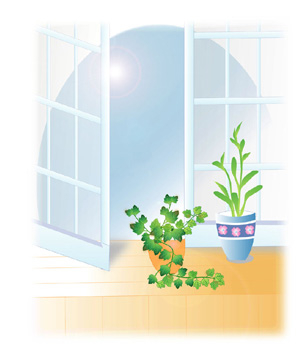
さてと、6月に入ってあっという間に10日目に成ろうかと言う、何とも日々の経過が早くて、もう少しゆったりと時間が過ぎてくれないものかね~。![]()
私が良くネットサーフィンしてのぞき見している所に、『るいネット』といサイトがあるのだが、今日読んだ記事の中で共感出来る物が有ったので、ここでも紹介してみようと思う。
それは、
『一億総百姓化社会のススメ~日々の暮らしの中に、『農』の時間を(新しい「農」のかたち)』
という記事に成っている。
重複するが、記事の内容から
『知る、ではなく、発見する。
消費する、ではなく、生産する。
勉強はつまらないが、学ぶことは楽しい。』
とあり、
『生きる意欲につながるこれらの気づきが、「農」を通じて得られるということ』
と、繋がっていく。

だが、実際に『農』を実践しようと思っても、そう簡単には出来はしない。
先ずはリンクの記事を参照して頂きたい。
個人的意見であるが、農業を通してではなくても良いと私は考える。
農業と言うと先程も書いたが、一歩引いてしまうのではないだろうか。![]()
言い換えれば、『何かを育てる』事を自らが行う事をすれば良いと思うのだが。
子供に犬や猫を育てる事をさせていけば『![]() 命
命![]() 』の大切さを自分の心を通して味わうことに成る。
』の大切さを自分の心を通して味わうことに成る。
いわゆる体験学習だ。![]()
しかーし、現代では子どもたちの中でも大人でも、猫アレルギーや犬アレルギー等と言った現代病を発症する等して、ペットすら簡単には飼えなくなってきている。
少し脱線したかの様だが、根本は『![]() 健康体では無く成ってきている
健康体では無く成ってきている![]() 』という事なのだよ。
』という事なのだよ。
その原因の多くは『食』にある。
自ら食材を作るという事は、単一の食べ物を育てるという事だ。
未加工の食材、つまりは自然食材を自ずと育てて食すると言う事だね。
なぜそれが大事なのか。
そんな事は言わずもがなである。![]()
人の体組織、臓器を作り上げているのは食材である。
臓器が本来の機能を100%出せば、病は消えるのだよ。![]()
臓器とはその機能を持ってして『人体』を作り上げているのだからね。
食の欠陥が肉の欠陥を生み、その欠陥が元で臓器機能に欠陥が生じる。
健康が損なわれていく根本の原因としては、この『食』にある。

本来採らなくて良いもの、つまり![]() 余計な物
余計な物![]() を取り込んでしまっているのだよ。
を取り込んでしまっているのだよ。
と個人的に考えているのだがね。
まぁ、そんな訳で自然食品を自ら栽培して、栽培中の食材の変化を楽しみ、食すまでの香り、手触り、色合い、形...それらを五感を以て見つめていると一つの食材の持つ多様な個性が見えてきて、学校では習わなかった事を学ぶ事が出来る、体験学習がこの歳でも十分に出来るのだ。![]()
これが楽しいと言える授業ではないかな。![]()
イチゴが実ると近くに居るだけでその香りに酔いそうに成る。
ナスの葉はその裏に立派なトゲが突き出ている。
パプリカは今はピーマンと化しているが、いずれカラフルな色を醸し出してくれるはず。
実ったトマトは品種により楕円形や球体を成し、ベースグリーンで生育の心地よさを教えてくれるので、品種ごとの肥やし濃度も教えてくれる。
とまぁ、日々手入れをしていると栽培中の食材をその様な目で観ることが出来る。
立派なモニタリングではないか。![]()
私は水耕栽培で出来るだけ同じ条件の中で、色んな食材を育てられないかに注目して日々の栽培を行っているのだけど、葉物と実ものは結構違うからそう簡単ではないがね。
私が思い描く、軒下家庭菜園は個人が自ら食材を育てながら、その変化を楽しみ活かし、世話をしてあれこれ考えてそれぞれの個性を見出して、見慣れた野菜達のちょっとした個性を自分が栽培の中で発見する喜びに歓喜して欲しいのだよ。
食材の変化へのワクワク、手入れ作業のドキドキ...
そんな心の動揺を楽しむくらいの変化が生まれるのだがね。
たかだか家庭菜園での野菜栽培だろうけどさ。![]()
食材をどう観るか
これが大事なんだが
まっ、現代社会の生活リズムの中で十分満足な想いが出来ている人は、それで十分でしょうけど、自分という一人の人間を自ら楽しませる事をやってみたいと思うのであれば、この水耕栽培って結構自分の世界に人を引き込むまでに成る程、個性豊かな食材たちの変化を、正に身を以て楽しめるツールなのですがね。
そうは言っても所詮個人の価値観ですからなぁ~。![]()
今日の一枚。

もう一枚


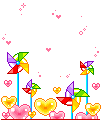
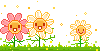

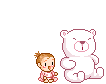






コメント